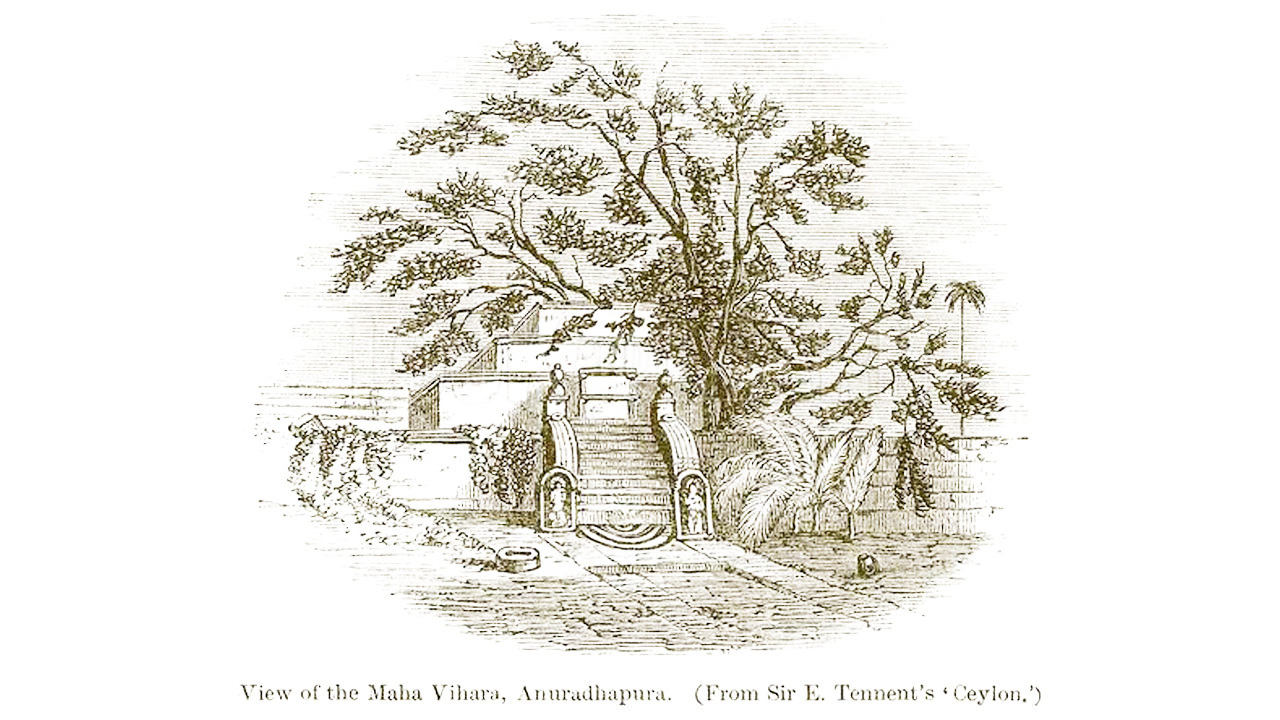アヌラーダプラ マハ ヴィハーラヤ
アヌラーダプラマハ ヴィハーラヤは、スリランカの上座部仏教にとって重要なマハーヴィハーラ、または大規模な仏教僧院でした。アヌラーダプラのデヴァナンピヤ ティッサ王 (紀元前 247 ~ 207 年) が首都アヌラーダプラに設立しました。ブッダゴーサ(西暦 4 世紀から 5 世紀)やダンマパーラなどの僧侶は、上座部仏教の教義の中心となるティピタカの注釈やヴィシュッディマッガなどの文書を執筆し、ここで上座部マハーヴィハーランの正統性を確立しました。マハーヴィハーラに住む僧侶はマハーヴィハーラヴァシンと呼ばれていました。 5 世紀には、「マハヴィハーラ」はおそらく南アジアまたは東アジアで最も洗練された大学でした。多くの国際的な学者が訪問し、高度に構造化された指導の下で多くの分野を学びました。
初期の歴史
上座部の 3 つの部門は、スリランカにおける仏教の初期の歴史のほとんどの期間、マハーヴィハーラ、アバヤギリ ヴィハーラ、およびジェータヴァナに存在しました。マハーヴィハーラが最初に確立された伝統であったのに対し、マハーヴィハーラの伝統から分離した僧侶たちはアバヤギリ ヴィハーラとジェータヴァナ ヴィハーラを設立しました。 AK ウォーダーによれば、インドのマヒシャーサカ派も上座部と同時にスリランカに定着し、後に上座部に吸収されたという。スリランカの北部地域も、ある時期にインドからの宗派に割譲されたようです。 『マハーヴァムサ』によれば、アヌラーダプラマハーヴィハーラは 4 世紀にアバヤギリ ヴィハーラの僧侶との宗派間紛争で破壊されました。これらの大乗僧たちは、アヌラーダプラのマハセーナを扇動して、アヌラーダプラヴィハーラを破壊させました。この結果、後の王はマハヤニンをスリランカから追放しました[要出典]。
マハーヴァムサが提供する伝統的な上座部仏教の記述は、5 世紀初頭 (西暦 399 年から 414 年の間) にインドとスリランカを旅した中国の仏教僧ファクシアンの著作とは対照的です。彼は西暦 406 年頃に初めてスリランカに入り、自分の経験を詳細に書き始めました。彼は、マハーヴィハーラが無傷であっただけでなく、3,000 人の僧侶が住んでいたと記録しました。彼はまた、マハヴィハーラで、羅漢の位を獲得した非常に尊敬されるシュラマナの火葬に個人的に立ち会ったことについても説明している。ファクシアンはまた、アバヤギリ ヴィハーラが同時に存在し、この僧院には 5000 人の僧侶が収容されていたと記録しました。西暦 7 世紀、玄奘三蔵はスリランカに両方の僧院が同時に存在していたことについても記述しています。玄奘三蔵は、スリランカの上座部の 2 つの主要な部門について書き、アバヤギリの伝統を「大乗スタヴィラス」、マハーヴィハーラの伝統を「小乗スタヴィラス」と呼んでいます。玄奘三蔵はさらに、「大乗ハーラヴァーシンは大乗を拒否し、高乗を実践するが、アバヤギリヴィハーラヴァーシンは高乗と大乗の両方の教えを研究し、大蔵経を広めている」と書いている。
その後の歴史
学者の中には、スリランカの統治者が上座部が伝統的なものであることを保証しており、この特徴はインド仏教とは対照的であると主張する人もいます。しかし、西暦 12 世紀以前には、スリランカのより多くの支配者がアバヤギリ上座部を支援し後援し、ファクシアンのような旅行者はアバヤギリ上座部をスリランカの主要な仏教伝統とみなしていました。アバヤギリ ヴィハーラが有力な上座部派であるという傾向は、西暦 12 世紀に変化し、マハーヴィハーラがパラッカマバーフ 1 世 (西暦 1153 ~ 1186 年) の政治的支援を得て、アバヤギリとジェータヴァナ 上座部の伝統を完全に廃止しました。その後、これら 2 つの伝統の上座部僧侶はロックを剥奪され、信徒に永久に戻るか、マハーヴィハーラの伝統の下で「修練者」 (sāmaṇera) として再出家を試みるかの選択が与えられました。リチャード・ゴンブリッチは、マハーヴィハーラの多くの僧侶もロックを解除されたと書いている。
年代記には彼がサンガを再結成したと書かれているが、この表現は彼がやったことがアバヤギリとジェッタヴァナ・ニカヤを廃止することであったという事実を覆い隠している。彼はマハー・ヴィハーラ・ニカーヤ寺院の多くの僧侶たち、他の二つの寺院の僧侶全員を釈放し、その後、後者のうちより優れた僧侶が現在「統一された」サンガの新参者となることを許可し、彼らはやがてサンガに再任されることになった。